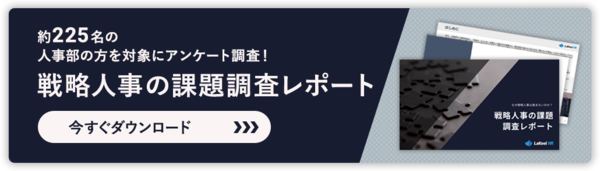戦略人事を進めるのに役立つフレームワークとは?活用の注意点もご紹介

経営戦略と人事戦略をリンクさせる「戦略人事」は、昨今の変化が激しい時代に適応できる優秀な人材の獲得や育成が求められる状況において、重要視されています。戦略人事を推し進めるためには、戦略を策定し、データに基づいた施策を実施、改善していくことが重要です。そこで役立つのが各種フレームワークです。
今回は、フレームワーク活用の意義や主なフレームワーク、人事戦略を立案する際の注意点をご紹介します。
目次[非表示]
- 1.戦略人事とは?フレームワーク利用の意義
- 1.1.戦略人事とは?
- 1.2.人事戦略との違い
- 1.3.人材戦略との違い
- 1.4.戦略人事の実施ポイント
- 2.戦略人事を効率的に行うためのフレームワーク
- 2.1.SWOT分析
- 2.2.TOWS分析(クロスSWOT分析)
- 2.3.CATWOE分析
- 2.4.ロジックツリー分析
- 2.5.PEST分析
- 2.6.TOWS分析
- 2.7.PPM分析
- 2.8.根本原因分析
- 2.9.ケプナー・トリゴー法
- 3.フレームワークを活用して人事戦略を立てるときの注意点
- 4.戦略人事を実行するためのステップ
- 4.1.1.企業のビジョンと目標の明確化
- 4.2.2.現状分析
- 4.3.3.人事戦略の策定とアクションプラン作成
- 4.4.4.周知・実行
- 4.5.5.評価とフィードバック
- 5.まとめ
戦略人事とは?フレームワーク利用の意義

まずは戦略人事の定義と、フレームワークを利用する意義を確認しておきましょう。
戦略人事とは?
戦略人事とは「経営戦略や事業戦略と連動した人事戦略を策定し実行すること」を指します。優れた経営戦略や事業戦略であっても、それを実行するヒトがいなければ実現がむずかしいという考え方の下、人事戦略を立て推進していきます。
戦略人事を進めるにおいて欠かせないのが、経営戦略や経営ビジョンをもとに、それらの達成に必要な人材像を定めることです。そして、その人材像に合致した人材を確保・育成するために必要な戦略を検討し、計画を立て実行していきます。
人事戦略との違い
戦略人事と人事戦略は似た概念ですが、目的とアプローチに違いがあります。人事戦略は、採用・育成・評価・報酬などを中長期的に計画し、企業の成長を支えるための方針を指します。一方、戦略人事は経営戦略と密接に連携し、人材を活用して企業の競争力を高めることを目的とします。
人事戦略は制度や仕組みを整える計画的な枠組みであるのに対し、戦略人事は市場環境や経営状況に応じて迅速に調整し、柔軟に人材配置を行うダイナミックなプロセスが求められます。特に、変化の激しい現代では、戦略人事の重要性が高まっています。
企業が持続的な成長を遂げるためには、人事戦略と戦略人事を組み合わせ、経営戦略と連動した人材マネジメントを実践することが不可欠です。
人材戦略との違い
戦略人事と人材戦略は、どちらも企業の人事領域に関わる重要な概念ですが、視点と目的が異なります。人材戦略は、企業の長期的な成長に向けて、採用・育成・評価・配置などの人事施策を体系的に整えることを目的とします。主に社内の人材資源の最適化に重点を置き、どのような人材を確保し、どのように育成していくかを計画します。
一方、戦略人事は経営戦略と密接に結びつき、企業のビジョンや事業戦略の実現を支援するために人材を活用することを重視します。市場環境の変化や競争優位性の確立を前提とし、経営課題に即した組織づくりや人事施策を柔軟に展開する点が特徴です。つまり、人材戦略は計画的な人材管理の枠組みであり、戦略人事は企業の競争力を高めるための動的な人材活用の仕組みと言えます。
戦略人事の実施ポイント
戦略人事を実施する際に必要になる人事戦略は、経営戦略に基づく立案が求められます。従来の人事戦略と異なるのは、経営戦略とリンクしているかどうかです。戦略人事における人事戦略は、経営戦略を実現するためのものだからです。
また、戦略人事における人事戦略の立案にはフレームワークを利用することで効率的に行うことができます。
フレームワークを利用することで、客観的な視点で現状課題の把握や情報分析が可能になるためです。そして洗い出された課題や分析結果を社内で共有することで、共通の枠組みとして活用することができます。これは戦略人事を全社的に推し進めていく際に重要な指標となり得ます。
またフレームワークを利用することで、洗い出された複数の課題について、原因との関係性を見極めやすくなるというメリットもあります。
戦略人事を効率的に行うためのフレームワーク

戦略人事の実現に向けた人事戦略を立案するにおいて、役立つとされている主なフレームワークを、どのような点で役立つのかも合わせてご紹介します。
SWOT分析
SWOT分析とは、自社を取り巻く内部と外部の環境における「S(Strength/強み)・W(Weakness/弱み)・O(Opportunity/機会)・T(Threat・脅威)」に分類して分析する手法です。
これらの4つの要素について自社が置かれている状況を整理することで、客観的に自社のスキルや能力の過不足を把握できます。
TOWS分析(クロスSWOT分析)
TOWS分析とは、SWOTの発展型で、SWOT分析で明確になった要素をかけ合わせることで、より具体的な戦略を策定できる手法です。例えば、機会と弱みをかけ合わせることで、現状の市場においてどのように自社の弱点を補強できるかを具体的に思考できます。
CATWOE分析
CATWOE分析とは、「C(Customers:問題の対象)」「A(Actors:問題に関わる人)」「T(Transformation process:問題解決に必要なプロセス)」「W(World view:問題解決に影響する価値観)」「O(Owner:問題解決の責任者)」「E(Environmental cunstraints:環境による制約)」の6つの要素を洗い出すことで、複雑な問題や状況を深く掘り下げることが可能になる手法です。問題に関わる人物やグループ、要因を特定しやすいため、「誰が何をすべきか」が見えてくることで、戦略策定に活かすことができます。
ロジックツリー分析
ロジックツリー分析とは、目標を一つ掲げた際に、それに達成に必要な要素を分解してツリー形式で展開していくことで、問題の真の要因や課題解決のための手段を特定していく手法です。問題の要因を広く深く具体的に掘り下げる手法のため、全体像を把握し易く、原因の根本を発見することが簡単になり、戦略策定および計画の具体的な実行方法を検討するのに役立ちます。
PEST分析
PEST分析は、政治(Political)、経済(Economic)、社会(Social)、技術(Technological)の4つの外部環境要因を評価する手法であり、人事戦略においても重要です。例えば、政治的要因では労働法の変更が採用や解雇のポリシーに影響を与え、経済的要因では景気の動向が給与や福利厚生の見直しを促します。また、社会的要因では多様性や働き方改革が求められ、技術的要因ではリモートワークやデジタルスキルの需要の変動が影響します。
TOWS分析
TOWS分析は、企業の外部環境(脅威と機会)と内部環境(強みと弱み)を総合的に評価し、戦略を策定する手法です。人事戦略においては、企業の強み(S)を活かして外部の機会(O)を最大限に利用する方法を考えたり、弱み(W)を補うための内部改革を行い、外部の脅威(T)に対処する方法を模索します。例えば、強みとしての優れたリーダーシップを活用し、業界の新しいトレンドに対応するための人材育成プログラムを導入することが考えられます。
PPM分析
PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)分析は、企業の事業や製品群を「花形」「金のなる木」「問題児」「負け犬」の四象限に分類し、資源配分を最適化する手法です。人事戦略と関連させると、各象限に適した人材配置や育成が可能になります。例えば、「花形」には高いスキルと経験を持つ人材を配置し、「問題児」には革新的なアイデアを持つ若手を投入することで成長を促進します。
根本原因分析
戦略人事を効果的に進めるためには、表面的な課題に対処するだけでなく、その根本原因を特定し、適切な施策を講じることが重要です。根本原因分析とは、組織内の問題やパフォーマンス低下の真因を探るプロセスであり、短期的な対応ではなく、持続可能な改善を実現するための手法です。例えば、離職率の増加が問題視された場合、その背景にある職場環境や評価制度の不備、キャリアパスの不透明さなどを掘り下げて分析することが求められます。この際、5WHY分析やフィッシュボーンダイアグラムといったフレームワークを活用することで、問題の本質を体系的に整理できます。
ケプナー・トリゴー法
ケプナー・トリゴー法は、問題解決や意思決定の際に論理的に分析し、最適な解決策を導き出す手法の一つです。問題の原因特定や対策の優先順位を明確にすることができ、戦略人事においても、組織課題の解決や適切な人材配置の判断に活用できます。この手法では、まず問題の特性や影響範囲を整理し、その後、発生原因を明確にしていきます。次に、可能な解決策を比較・評価し、最も効果的な選択肢を決定するプロセスを踏みます。例えば、離職率の上昇に対する施策を検討する際、現状のデータを分析し、離職の要因を特定し、それに対する具体的な対策を立案することが可能になります。ケプナー・トリゴー法を用いることで、感覚的な判断に頼らず、データや論理に基づいた人事施策を実行できるため、組織全体の成長を促進する重要な手法となります。
フレームワークを活用して人事戦略を立てるときの注意点

フレームワークを活用して人事戦略を立てるときには、次の注意点を押さえて実施することをおすすめします。
フレームワークはあくまでも手段ととらえる
フレームワークを用いて分析しているうちに、フレームワークの分析そのものが目的となってしまうことがあります。フレームワークはあくまでも人事戦略を立案する際の手段にすぎません。また、フレームワークによる思考を完璧に行おうとすると、無理にフレームワークの枠組みにあてはめようとする意識が働き、現状を正確に把握できなくなる恐れもあります。フレームワーク活用の目的を把握したうえで人事戦略の立案を検討しましょう。
フレームワークを利用するにはまずデータが必要
フレームワークを利用するには、社内の様々なデータが必要になってきます。まずは社内のデータや市況データを集めることが先決です。その際には人事システムが役に立ちます。社内のデータを一元管理し、それを可視化・分析できる機能を有する人事システムであれば、フレームワーク活用も迅速に進むでしょう。
戦略人事に基づく人事戦略立案には、人事戦略の方針や目標設定も必要不可欠です。その上で、フレームワークはプロセスに活用していくのがポイントです。
戦略人事を実行するためのステップ

戦略人事を実行するためのステップは、企業のビジョンや目標を達成するために人材を効果的に活用する枠組みを構築することを目的としています。以下はそのための主要なステップです。
1.企業のビジョンと目標の明確化
企業のビジョンと目標の明確化は、戦略人事を実行するための重要なステップです。まず、企業の長期的なビジョンを明確にし、それが組織全体の方向性を示す指針となるようにします。次に、ビジョンに基づいて具体的な目標を設定し、これらが達成可能で測定可能であることを確認します。目標は、組織の各部門や個人の行動と連携し、全体のパフォーマンスを向上させるための基盤となります。そのうえで、ビジョンと目標を社内で共有し、全員が一体となって取り組む環境を整えます。
2.現状分析
戦略人事における現状分析には、前述したようなフレームワークが有効です。例えば、SWOT分析は組織の強み、弱み、機会、脅威を明確にし、人事戦略の方向性を見極める手助けをします。次に、PEST分析は政治、経済、社会、技術の外部環境要因を評価し、人事戦略に影響を与える外的要因を把握します。さらに、そのほかのフレームワークを組みあわせ分析することにより、従業員のパフォーマンスとポテンシャルを評価し、タレントマネジメントの基盤を築くことが可能です。
3.人事戦略の策定とアクションプラン作成
人事戦略の策定は企業のビジョンやミッションに基づき、長期的な人材の方向性を定めるプロセスです。具体的には、現状の人材の分析から、必要なスキルや人数、組織文化の改善点を明確にします。また、市場動向や競合他社の状況も考慮し、企業が持続的に成長するための人材戦略・人事方針を設定します。
その上で、策定した人事戦略を具体的な行動に落とし込むためのアクションプランを作成します。これは、目標達成に向けた具体的なステップを示すもので、期限や責任者を明確にすることが求められます。採用、育成、評価制度の見直しや、従業員のモチベーション向上施策など、具体的な施策を計画します。これにより、戦略が現場で実行され、組織全体が一体となって目標に向かうことが可能となります。定期的な進捗確認とフィードバックも重要であり、状況に応じた柔軟な対応が求められます。
4.周知・実行
戦略を全社員に周知し、理解と協力を得るためのコミュニケーションを行います。従業員のエンゲージメントを高めるための活動も重要です。そのうえでアクションプランを実行し、その進捗を定期的にモニタリングします。
5.評価とフィードバック
戦略の効果や成果を評価し、フィードバックを行います。これにより、次の計画策定に向けた学びを得たうえ、目標達成に向けて継続的に改善を行います。
まとめ
戦略人事を推し進める際に役立つフレームワークや活用のポイントをご紹介しました。フレームワークを利用するのに必要なデータは人事システムを活用して揃えるのが効率的です。
「LaKeel HR」は、戦略人事を推進するのを強力にサポートする人事システムです。人材管理・データ分析・施策実行までを一つのシステムでまるごと管理することが可能です。フレームワークを活用するのに必要なデータはLaKeel HRを用いることで、容易に扱うことができます。詳細はぜひサービス紹介ページをご覧ください。