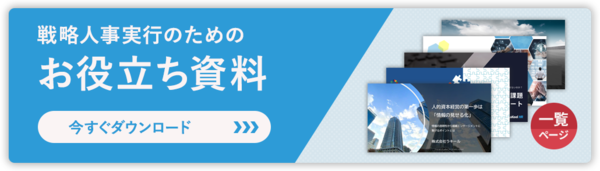ジョブ型雇用のメリットとは?企業と従業員にとっての利点を解説

「仕事=ジョブ」を明確に定義して雇用する手法であるジョブ型雇用は、欧米では主流であり、日本でも認知されつつあります。
今回は、ジョブ型雇用のメリットと共に、デメリットも合わせてご紹介し、さらにメリットを得るために日本企業に必要なことについてご紹介します。
目次[非表示]
- 1.ジョブ型雇用のメリットとは?
- 1.1.ジョブ型雇用のメリット
- 2.ジョブ型雇用のデメリット
- 3.ジョブ型雇用のメリットを享受するために
- 4.ジョブ型雇用の導入手順
- 5.まとめ
ジョブ型雇用のメリットとは?

ジョブ型雇用は、「仕事=ジョブ」を軸にして人を雇用する手法であり、あらかじめ仕事内容や責任範囲、勤務場所などを明確に定めた上で雇用します。
ジョブ型雇用が注目されている背景として、DX人材などの高度な専門スキルを持つ人材の必要性が高まっているとともに、従来の年功序列や終身雇用の文化は、変化が激しく先行きが見えにくい現代の環境に合わなくなってきたこと、多様な働き方を推進する働き方改革を進めやすいことなどが挙げられます。
ジョブ型雇用のメリット
ジョブ型雇用のメリットは、企業・従業員それぞれの立場から次のことが挙げられます。
【企業にとってのメリット】
・専門性の高い人材を採用・育成できる
・組織の生産性・競争力向上につながる
・職務内容の同意の上での雇用によりミスマッチを防止できる
企業にとっては、経営戦略や人事戦略に基づく専門性の高い人材を採用・育成しやすくなり、生産性・競争力の向上につながります。また雇用時に労働条件だけでなく職務内容の同意も得るため、入社後のミスマッチを予防することができます。これらの結果、環境変化に即した人材戦略が可能になります。
【従業員にとってのメリット】
・専門性・スキルの向上がしやすい
・入社後に職務内容のミスマッチを感じることが少ない
・決められた仕事のみ行える
・転勤や異動がほぼない
・年齢や入社歴に関係なくスキルを向上させれば昇給・昇格が期待できる
従業員は、「仕事」を軸に雇用され、決められた仕事のみ行い、自身の専門性・スキルを思う存分伸ばすことが可能です。入社後も職務内容に関する不一致を感じにくいでしょう。転勤や異動はほぼないと言ってよく、スキルのレベルが上がり、上位ポジションに空きがあれば、年齢によらず、昇給・高額収入が期待できる点もメリットといえます。
ジョブ型雇用のデメリット

ジョブ型雇用のデメリットも合わせて確認しておきましょう。
【企業にとってのデメリット】
・契約外の業務を任せられない・配置転換がしにくい
・採用の難易度やコストが上がりやすい
・優秀な人材が流出しやすい
・組織の一体感が失われやすい
・マネジメント・経営幹部候補の育成が困難
雇い入れ時には明確な職務の範囲を決めているため、契約外の業務を任せたり、配置転換を行ったりすることができず、柔軟性が失われます。また、高度なスキル人材を獲得するにはコストが高くなりがちです。
さらに、従業員はあくまで仕事に対するスキルを発揮しているにすぎず、環境や報酬が上回る他の職場が見つかれば、容易に移ってしまう恐れがあり、優秀な人材が流出しやすくなるといえます。人材の流動性が高まるとともに、各従業員がスキルに特化することで、組織の一体感が失われやすくなります。
また従業員が個々に専門スキルを磨き上げるのに集中すると、会社のマネジメント層や経営幹部候補の育成が困難になってきます。
【従業員にとってのデメリット】
・スキルを上げなければ昇給や就業機会を失う
・職務切り替えすると給与が下がるリスクがある
・総合的なスキルが身に付きにくい
ジョブ型雇用の従業員にとっては、常にスキルが報酬や仕事に紐づいているため、自己研鑽を怠ると職を失う恐れを感じます。また他の仕事がやりたくなった場合、積み上げてきた職務スキルと経験を手放すことになれば、給与が下がるリスクがあります。
また、専門スキルに特化した自己研鑽や研修を受け続けることで、かつてメンバーシップ型雇用で行われてきた集合研修で培うような、まんべんなく身につく総合的なスキルを獲得しにくくなります。
ジョブ型雇用のメリットを享受するために

日本企業がジョブ型雇用のメリットを存分に享受するためには、次の点を押さえることがポイントです。
無理に移行せず現行制度と併用する
これまでメンバーシップ型雇用が根付いてきた企業においては、いきなりすべての職種においてジョブ型雇用に移行するのではなく、現行制度と併用することで、徐々に浸透させていくことができます。エンジニア職やマネジメント層などに限定してジョブ型を採用することがポイントです。
抜本的な制度変更を長期的に計画する
ジョブ型雇用を導入するにあたっては、昇給・評価制度、採用関連などさまざまな制度を根本的に変える必要が出てきます。しかし安易に変更することは従業員からの抵抗を生むこともあるため、長期的に計画し、慎重に従業員の声も取り入れながら進めていくことが大切です。
タレントマネジメントシステムでスキルを可視化する
社内の人材データをスキルの観点から集めて一元化するタレントマネジメントシステムなどを活用して、社内のスキルを可視化することが有効です。各種戦略に基づき、必要なスキルの有無や育成・採用の必要性などを見極めることができます。
ジョブ型雇用の導入手順

ジョブ型雇用の導入手順は以下の通りです。
1.ジョブ型雇用を適用する職種・職務を決める
2.ジョブ・ディスクリプションを作成する
3.人事制度の策定や見直しを図る
4.運用・フィードバックと改善を繰り返す
5.関連する制度や人事施策を見直す
ジョブ型雇用をどの職種や職務に導入するのかの範囲を定め、「ジョブ・ディスクリプション」を作成します。職種、役職・ポジション、職務内容、目標と評価方法、必要な資質・スキル・資格、給与、給与体系などを記載します。また職務別や等級別の報酬制度や、教育制度、採用計画の策定や見直しを図ります。
運用開始後は、従業員からのフィードバックを元に導入効果を評価し最適化していきましょう。そして関連する制度や人事施策の見直しも長期的な視野で取り組むことが肝心です。
すでに日本企業の多くがジョブ型雇用の導入を進めています。下記のコラムでは、3つの日本企業の導入事例も解説していますので、合わせてご覧ください。
関連リンク|ジョブ型雇用とは?メリット・デメリットや事例などをご紹介
まとめ
ジョブ型雇用のメリットと共に、デメリット、メリットを享受するためのポイントについて解説しました。メリットを確実に得て、市場における競争力をつけていくために、最適化していくことがポイントです。
統合型人事システムの「LaKeel HR」では、人材データの分析などタレントマネジメントに必要な機能も備えております。社内に散らばる様々な人事データを集めて一元管理し、人事評価分析、ハイパフォーマー分析や、退職リスク予測、採用分析など多様な切り口でデータの分析が可能です。
またLaKeel HRでは、戦略人事を実行するためのお役立ち資料を豊富にご用意していますので、ぜひご覧ください。